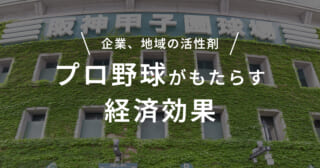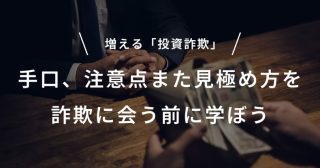2023年になって自転車のヘルメットの努力義務化があった。
街中を歩いている警察官などの公務員は必ずヘルメットをしており、子供を乗せたママチャリの人もヘルメットをしている人はだいぶ多くなった。
努力義務化ということはしないと罰則を受ける?、した方が良いのか?
ルールが変わっていまいちよく分からないことも多いと思います。
今回は自転車のヘルメットの努力義務化の背景やヘルメットはすべきかなどをまとめました。

努力義務ってなに
今回の法律改正でまず、”努力”義務ってなんなのか
という疑問が出たと思います。
努力義務は罰則にならない
では努力義務とただの義務の違いと考えていきますが、
一番の違いは努力義務は罰則にならないことでしょう。
例えば、車に乗るためには免許証の取得と携帯を義務つけられています。
これらを違反した場合は罰金などの罰則が発生しますが、
自転車のヘルメット着用に関してはこの罰則がありません。
もちろん、安全面ではすべきかもしれませんが、
日本は習慣としてヘルメット着用をしておらず、なかなか完全義務としての導入は難しかったのでしょう。
ヘルメットの着用はなぜ努力義務化されたのか?
自転車事故のリスクとヘルメットの重要性
自転車は古くは明治時代、世界との交流が多くなったころから日本に浸透し、
生活用品だけでなく、競輪、クロスバイクなど競技としても親しまれた存在でした。
しかし、昭和、平成に入り自動車の利用台数の増加、合わせて交通事故が増えていったのです。
統計的にも実は自転車関連の交通事故は2割を占めており、
手軽な乗り物のために子供たちの利用も多く、自転車に乗る際に安全に注意する必要が生まれてきました。
そのため、2023年4月に国としてヘルメット着用の努力義務が導入されたと考えられます。
自転車事故では頭部へのけがが多く、ヘルメットがなければ重傷を負う可能性も高まります。
外国では完全義務化されていることもある
自転車のヘルメット着用の義務化について、国外での動向を見てみましょう。
海外では、ヘルメット着用の義務化が進んでいる国もあります。
例えば、オーストラリアやニュージーランドでは、
自転車に乗る際にはヘルメットの着用が完全義務化されており、
実際に事故によるケガ、死亡リスクの軽減に貢献していると考えられています。
しかし、実際には義務化に対し賛否が分かれています。
賛成派は、もちろんヘルメットの着用によって事故時の頭部へのダメージを軽減できると主張していますが、
一方、反対派は、ヘルメット着用の義務化が自転車利用者の自由を制限するものだと主張しています。
確かに、いちいち被るのは面倒ですしこの主張も理解はできます。
実際に日本も努力義務なんで、めんどくさいからつけてない人は結構多いです。
なぜ自転車の需要が上がったのか
日本ではここ数年で自転車の需要が格段に上がったと考えられます。
その原因を見ていきましょう。
コロナ禍
まずは、新型コロナウイルスのパンデミックにより、自転車の需要が急増しました。
電車、バスなどは密な環境のため感染の可能性が高く、
コロナ初期は死亡リスクもあったため自転車で移動する人が増えました。
健康意識
また、健康意識の高まり共に自転車通勤をすることでの
運動目的でも注目されました。
エコロジー、SDGs
世界的にここ数年で地球、環境に優しい取り組みをするというエコロジー、という考えが広まってきました。
そのため、環境にも優しい交通手段としては自転車が注目されました。
ビジネス利用、ウーバーイーツなども
また、自転車による配達業の需要が大きくなったのも原因でしょう。
特にウーバーイーツは、日本で大きな注目を集めたサービスではないでしょうか。
自転車ヘルメット努力義務化は新しい経済需要も?
自転車ヘルメット着用問題は一見すると自転車業界とヘルメット業界?だけの問題と考えがちですが、
実は他の業界にも影響はありました。
自転車保険
元々自転車保険は大手保険会社、自転車屋さんなどでありましたが
ヘルメット義務化による安全意識の向上から様々な企業にて新しい自転車保険が生まれました。
また、保険の中にはまた中にはヘルメット着用をしていないと適用されない場合もあり、
自転車を取り巻く認識が変わったと思います。
電動キックボード
また、皆さんは電動キックボードには乗ったことあるだろうか。
初速だけ蹴り上げてしまえばあとは電動で走行する電動キックボードも自転車のブーム、ヘルメットの努力義務に乗って広まりました。
特に大きな差別点として、ヘルメット着用しなくてもいいところがある。
電動キックボードは特定小型原動機自転車(以下 特定小型原付)という新しい区分になり、
規定を満たすものであれば電動キックボードのヘルメットは義務ではないのです。
そのため、サービスは主にまだ都心部だけですが、
自転車との差別化もあり、
手軽な乗り物として徐々に浸透してきてます。
ヘルメットはしなくてもいい
さてこの記事では、自転車用ヘルメットの着用に関する努力義務化について、
なぜ義務化が行われたのか、背景などを追っていきました。
結論から言うと日本の今の法律ではヘルメットはしなくても補導、罰則などにはなりません。
ただし、ヘルメット努力義務化が始まった背景には交通事故の増加が原因とされており、
事故に巻き込まれて死ぬかもしれないならヘルメットを着けるべきというのも事実です。
また、今回の改定で自転車保険などの中にはヘルメット着用をしていないと保険適用にならない。
などルールが変わったこともあります。
そのため、生活とリスクのバランスをしっかりと確認しながら判断しましょう。
このページを最後まで読んでくださってありがとうございます。
よろしければ、他にも色々と考察しているので読んでみてください。
また、私のLINEアカウントでは、本当に安心して行える資産運用の方法をお伝えしています。
ご興味ありましたら、ぜひ友だち登録をしてご連絡ください。
きっとあなたの為になると思います。