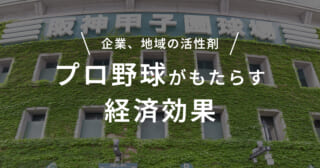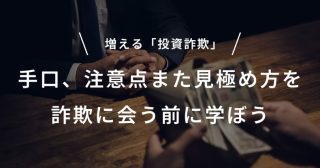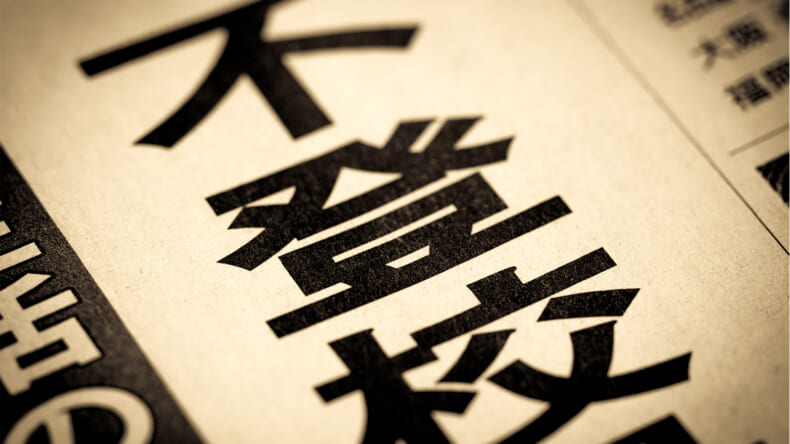
文部科学省は2022年度の小中学生の不登校者数を29万9千人と発表した。
この数値は2021年度の約24万人から22%の増加もしているのだ。
また実は2021年度の数値も前年より約5万人増えており、
不登校者数値はずっと増加傾向にある。
少子高齢化で子供の人数は減ってきているのに、
不登校者数はあり得ない割合で増加している。
果たして国や教育現場はこの危険性を理解しているのだろうか。
なぜ不登校者は増えている?
不登校とは、学校に通わずに学習機会を逃している状態のことを指します。
不登校の定義は厳密にはありませんが、
一般的には学校に通わない期間が30日以上続く場合に不登校とされます。
そのため、一時的な精神疾患、体調不良とは違い、学校というコミュニティに中長期的に関わらない状態です。
多くの人は学校のコミュニティに関わらないこと自体にストレスを感じるでしょうが、
不登校となったものは全く逆な状態と言えます。
原因とされていること
学校内の人間関係
まず、学校での人間関係の問題が一つの原因と考えられます。
いじめや友達関係のトラブルなど、学校での人間関係がうまくいかないことで、
子供たちは学校に行くことを嫌がるようになります。
また生徒間だけでなく、教諭との関係にもストレスを感じる場合もあります。
特に学校は約30人の生徒と教師一人という限られたコミュニティを約一年間強制されます。
コミュニティが合わなくても基本的に移動など配慮されることは少なく自己解決を要求されることが多いです。
このような環境は自己管理がまだ難しい小中学生には酷なことになる場合があり、
状況に耐えられず不登校となってしまうことがあります。
家庭環境
次に、家庭環境の問題も不登校の原因となります。
家庭内での問題や家族との関係の悪化などが原因で、
子供たちは学校に行くことが辛くなります。
一見すると家庭の問題なのになぜ不登校?と思うかもしれません。
きっかけは当事者それぞれですが、例えば自分の家庭環境が他者よりも悪く、
その差を学校にいるとその差に吐き気を覚えてしまうなど、
自己同一性が確立されてない小中学年では学校と家庭環境は密接な関係にあります。
さて、実は不登校になる原因として考えられるのはこの程度のことだけなのだ。
しかし、小中学生にとって学校と家庭は世界のすべてである。
それらが自分にとって居心地の悪いものになってしまったらその世界を否定してしまうのは当然ではないだろうか。
不登校が進むと
さて不登校またはいじめのようなものが進むことによる若者の影響を見ていこう。
学力の低下、就業機会の損失
学校は子供たちが学ぶための重要な場所です。
教師からの指導や他の子供たちとの交流を通じて、知識やスキルを習得することができます。
しかし、不登校の子供たちはこの学習の機会、経験を逃してしまいます。
その結果、学力の低下や学習意欲の減退が起こり、
将来的に自身の生活力の低下、収入減など幸せになる選択肢が減ってしまう可能性があります。
コミュニティ、コミュニケーションの経験機会の損失
また、学校は社会的なスキルを身につける場でもあります。
学校では、クラス、部活などコミュニティを作り他の子供たちとの関わりやグループ活動を通じて、
コミュニケーション能力や協調性を養うことができます。
不登校の生徒は基本的にこれらのコミュニティにストレスを感じるため不登校になっているわけではありますが、
若いうちにコミュニティに属してコミュニケーションや自己表現をすることは人生においてとても大事です。
不登校の生徒はその機会を失ってしまうため、
社会的なスキルの発達が遅れたり、孤立感を感じたりする可能性があります。
家出などに伴う悪影響を与えるコミュニティへの接触
不登校の多くは家庭、学校などに自分の居場所を感じません。
そのため、家出、SNSなど別のコミュニティで人間関係を求める傾向にあります。
健全なコミュニティ、人との関わりなら問題ないでしょうが、本人に悪影響を与える場合もあります。
特に売春、ドラック、未成年飲酒など犯罪に巻き込まれる場合もあり、
将来的にその若者の人生を狂わせてしまう可能性があります。
学校復帰への支援策と取り組み
さて、不登校を増やさないためにも、
教育現場では学校復帰への支援策と取り組みがなされています。
専門のカウンセラーや教育支援員の配置
いじめ、暴力など物理的な理由もありますが、不登校の多くは心の問題、環境の問題が原因です。
担当教諭や家庭でその問題に向き合えればいいですが、
生徒からすると彼らが問題の原因となっている場合もあります。
そのため、心のケアや学習支援を行い、個別のニーズに合わせた対応をする必要があり、
専門で人を設けることは重要とされています。
家庭、保護者へのヒアリング、連携
また、学校と保護者の連携も非常に重要です。
不登校の多くは家庭と学校でのコミュニティ、コミュニケーションに問題を抱えている場合があります。
そのため、保護者は不登校の原因を理解し、学校と協力して解決策を見つける必要があります。
また、現代は共働き、片親などどうしても自分の子供とコミュニケーションを取りづらい家庭も生まれてきています。
働き方や生活を変えることは難しいかもしれませんが、状況と影響を正しく理解して
例えば定期的に雑談、相談の場を設けることなど取り組みが必要でしょう。
学校復帰への支援センター
さらに、学校復帰に向けたプログラムや施設も必要です。
例えば、一時的な学校や学習支援センターを設けることで、子供たちが学校に戻る準備をすることができます。
多くの不登校者は学校というものに恐怖や不安を抱えています。
そのため、前段階で似たような環境で慣れて貰ったり、学業をしっかり学び自信に繋げてもらうことが大事です。
多様化と少子化の時代にはそもそも合わないのでは
さてここからは筆者の意見にはなるが、そもそも学校という制度は現代に合っているのか考えてみたい。
LGBTQなどあり方の多様化
今までの日本の教育は、協調性、共感性など
コミュニティ、グループとして同一であることが誇張、強制された傾向があった。
これは高度成長期において人口増加、学力の向上など
国全体での地力の底上げを目的にした政策、思想が根底にあるのだろう。
確かに昭和などは一学年が数百人いるなど若者の母数が多く、
そのような規格化された考え、教育方針が必要だったのかもしれない。
しかし、現代においては個性を大事にする傾向がある。
特にLGBTQなど性自認は最近では強制される勢いでそのあり方が認められているようになっている。
しかし、これは自己同一性が不安定、他者との距離感が把握できない小中学生などでは
本当に気を付けないといけない。
思わぬ発言で傷つけてしまったり、自分の存在に自信が持てなくなってしまうなど、
自己形成において取り返しのつかない事態になってしまう。
しかし、規格化、同一化を前提とした日本の学校教育においては
この思想の違いに教諭や保護者が対応できるのも限界があるのではないだろうか。
少子化によるコミュニティ形成の難しさ
日本の教育機関はクラス、学校、地域と枠組みを設けて閉鎖的に教育活動を実施する傾向がある。
物理的問題から地域などは仕方ないかもしれないが、
クラス、学校という閉鎖的コミュニティが生徒にとって満足できる、居場所を感じるかは疑問である。
今までは若者の母数が多かったため、
なんだかんだ自分の居場所となる人間関係やコミュニティを作れたかもしれない。
しかし、少子化が進んだ現代においては
自分の場所と感じるコミュニティを見つける、作るのは難しくなってきているのではないだろうか。
コミュニティの生成、所属を若いうちからすることは
社会に出て仕事や家庭など意図しないコミュニティに属するためにも必要な経験であり、正直学業より大事である。
このようなコミュニティの機会を失わせている可能性は今の学校教育には存在するのではないだろうか。
働き方の多様化、愛情不足
また家庭環境の多様化に対しても学校や教育機関は対応できていないのではないだろうか。
人の成長は、身体は食べたもので育ち、心は貰った言葉で育つ。
現代は共働き、片親など子供を持てる家庭状態が多様化しており、
家庭だけではどうしても子供とのコミュニケーションが不足してしまう場合がある。
学校にこれを求めるのは正直酷なのかもしれないが、
現実問題としてコミュニケーション不足による愛情不足はある。
また、現代の残酷でもあり素晴らしい部分として愛情不足な人でも子供を持ててしまうという問題もある。
経済的に考えた場合、人口が増加することはいいことであるため、どんな人でも家庭を持てるべきである。
しかし教育的観点から考える場合は、これは危険性を孕んだ状態である。
愛情不足、コミュニケーションを十分に経験してない人は
その後も他者とのコミュニティ形成、コミュニケーションがうまくできないケースが多く、
それは自分の子供にも同様である。
特に幼い子供は自分の親は絶対的に正しい存在でもあるため、
結果的に教育が不十分な人が生まれてしまうことがある。
そのため、コミュニケーション不足にならないように
学校や社会が個人と真摯に向き合い積極的に向き合わなければならない。
このままでは社会は崩壊するだろう。
さて今回は不登校の増加から見えてくる教育現場の問題、社会的問題などを考えて行きました。
経済的に社会的には少子化による人口減少が叫ばれており、こどもを持ちやすい環境作り、制度の改革が進んでいる。
しかし、生活変化、価値観の多様化などに伴い、
現代の家庭環境、学校では良い教育、経験が与えられず、不登校を増やしているという事実もあります。
産んで増やしてもみんな不登校になってしまうのなら意味はないのではないでしょうか。
不登校、いじめなどは当事者、関係者しか影響を与えづらい問題でもありますが、
ちょっとした言葉や居場所を作ることでも救われる若者は多いでしょう。
本当に日本経済、社会と良くするためにはまずは困っている人に声をかけることから始めるべきなのかもしれません。
このページを最後まで読んでくださってありがとうございます。
よろしければ、他にも色々と考察しているので読んでみてください。
また、私のLINEアカウントでは、本当に安心して行える資産運用の方法をお伝えしています。
ご興味ありましたら、ぜひ友だち登録をしてご連絡ください。
きっとあなたの為になると思います。