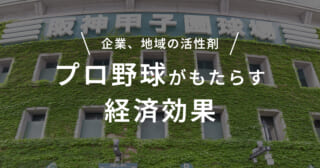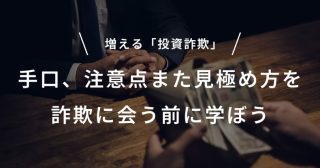最近値上げしていないものを探すのが難しい。
食材やガソリンは燃料の高騰、異常気象などあるので仕方がないという気持ちは生まれる。
しかし、税金や保険料の値上げはいまいち納得できないのは自分だけだろうか。
行政や自治体の財政は分かりやすいものではない部分も多くなかなか受け入れがたい。
そんなわかりにくい財政の問題で気になったニュースがあった。
今回はそのニュースにあった健康保険組合が赤字を抱えているという問題について掘り下げていきたい。
さて、読者の中には
「会社に言われたままとりあえず入ってけどよくわかってない」
という人もいるのではないだろうか。
実は筆者も調べてみるうちに知らなかったことが多かったのでその一人だったりする(笑)
そのため、一旦「健康保険組合」についておさらいをしよう。
健康保険組合?
健康保険組合は、日本の国民皆保険制度の一環として設立された団体であり、国民皆保険制度は、日本国内のすべての人々が健康保険に加入し、医療費の一部を負担することで、誰もが必要な医療を受けることができる制度です。
一定の地域や業種などの共通の特徴を持つ人々が集まり、共同で健康保険に加入する組織です。
組合員は、組合に年会費や保険料を支払い、その代わりに組合から医療費の補償を受けることができます。
また、組合員の健康を守り、医療費の負担を軽減することも目的としており、病気やけがなどで医療を必要とした場合に、補償を受けることができます。
また、予防接種や健康診断などの健康増進活動も積極的に行われています。
健康保険組合は、地域の特性や組合員のニーズに応じて、さまざまな保険制度やサービスを提供しています。
例えば、特定の病気に対する補償や、妊娠・出産に関するサポートなどがあります。
会社、業界によって差はあるが日頃の医療費の負担、健康診断など様々なサポートを受けられ、今の日本にはなくてはならない仕組みと言えるだろう。
赤字の組合が4割?原因は
さて、その健康保険組合が最近ある発表をあげており、大企業が加入する健康保険組合の2022年度の決算見込みにて40.4%が赤字だったと発表したのだ。
赤字?つまり最悪今まで払ってもらった医療費などが自己負担になってしまうのか?
この問題はかなり深刻であり、その原因となるものについて考えていきたい。
1.医療費の増加
日本の医療費は年々増加しており、高齢化社会による医療需要の増加や新たな医療技術の導入などが要因となっています。
これにより、保険組合は医療費をカバーするための費用を増やさなければならず、赤字になる可能性が高くなります。
2.経営効率の問題
保険組合は適切な予算管理や経営戦略の立案が必要ですが、中には効率的な経営が行われていない組合もあります。
経営の無駄や不必要な経費の発生が赤字を招くことがあります。
3.組合員の年齢などのバランス
組合員の健康状態や年齢構成も赤字の要因です。
健康な組合員が多い場合は医療費が少なくなり、赤字のリスクも低くなります。
しかし、高齢者が多い組合や慢性的な病気を抱えている組合員が多い場合は医療費が増加し、赤字になりやすくなります。
以上のように、医療費の増加、経営効率の問題、組合員の健康状態や年齢構成などが健康保険組合の赤字の原因となっています。
これらの問題を解決するためには、効率的な経営や予算管理、健康促進活動の充実などが必要です。
対応策はあるのか
1.高齢者へお金を使いすぎている
さて、原因に対して様々なアプローチがあるが一番対策すべきは高齢者への補助の割合などの見直しではないだろうか。
高齢者は一般的に健康状態が弱くなり、様々な病気や症状に対処する必要があります。
そのため、医療費がかかることが多くなるのです。
高齢者の医療費は、診察料や検査費用、入院費用など、さまざまな費用が含まれます。
また、高齢者は通院や薬の処方箋の取得など、定期的な医療サービスを必要とすることが多いです。
これらの費用は、高齢者やその家族にとって負担が大きい場合もあります。
もちろん、ご年齢にどうしても医療費がかかることは仕方がないことだが少子高齢の現在、年齢と人口によって負担が発生しているのだから見直されるべきポイントだろう。
2.組合費の増額
端的な解決策としてはこれだろう。
一律で組合員から取るお金をあげてしまえばいいのだ。
しかし、そもそもこれは不景気である現在においては致命的問題である。
3.子供など若い世代への支援は強めるべき
組合からの出費が増えるため一見これは逆効果に見えるが長期的にはこれはかなり大事である。
そもそも少子高齢により子供が少ない今は子供、子育て支援は急務である。
考えても見てほしい、組合員が減ればその分一人当たり負担は増えるのだ。
組合員を増やすためには組合のメリットを増やし、母数を増やすしかない。
それを考えたら、子供に対して手厚い支援、保証は大事であり、長期的な組合の運営には必要なものである。
現実的には組合に期待するのは難しい?
1.少子高齢化が治らない限り自体は変わらない
しかし、おそらく組合に事態の修復を期待するのは難しいと考えられる。
組合の赤字額は年間4000億円ほどとなっており、現状これをすぐ補填するのは難しい。
また、高齢者が未だに色々なところで実権を握っているため、制度の見直しも期待は難しいだろう。
2.個人で備えるのが大事な時代
さて、もうこうなったら個人で自分の備えが大事になってくる。
医療費の負担は生活する上ではどうしてもかかってしまうため、対策としては保険や貯蓄が有効な手段ではないだろうか。
日本では様々な保険があり自分に合ったものを選んで備えることができる。
また、貯蓄じゃなく投資という選択肢も考慮すべきだ。
貯蓄の場合はどうしても日本円の価値に依存するため、最終的には損をしてしまう場合もある。
その点、投資は価値の上がる資産として持ち続けられるため、長期的な資産の確保にはお勧めだ。
投資に関してまとめた記事もあるため確認してもらいたい。
https://baitai-demo.site/finance/benefits-of-inve…w-to-get-started/
仕組み自体がもう限界なのかもしれない
今回は健康保険組合とその赤字について考えていきました。
日本が抱える少子高齢化、不景気など様々な理由で、健康保険組合は赤字となることが増えてきてしまった。
今後、様々な対策が取られるだろうが根本的な解決はすぐには難しく、何があってもいいように自分で備えていくのが大事になってくるのだろう。
このページを最後まで読んでくださってありがとうございます。
よろしければ、他にも色々と考察しているので読んでみてください。
また、私のLINEアカウントでは、本当に安心して行える資産運用の方法をお伝えしています。
ご興味ありましたら、ぜひ友だち登録をしてご連絡ください。
きっとあなたの為になると思います。