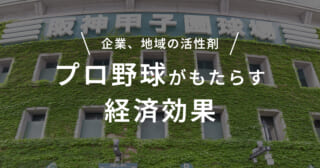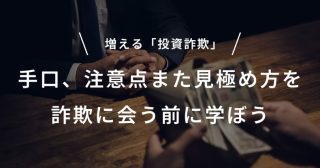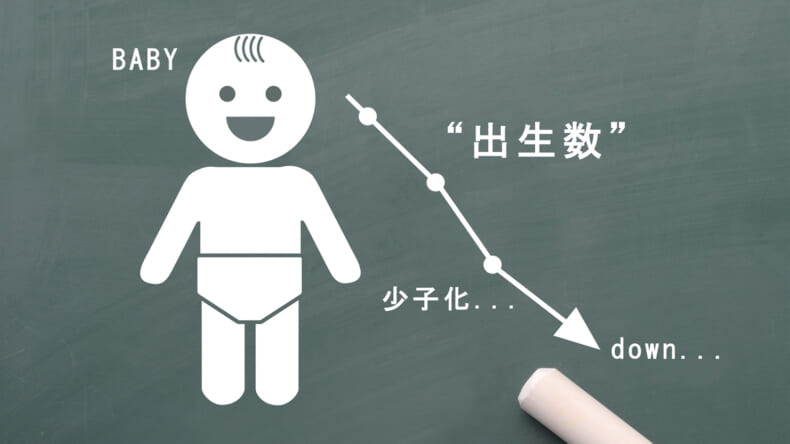
日本には様々な省庁がある。
外務省、総務省、金融庁、消費者庁など漢字ばかりで目がチカチカするが、
最近はスポーツ庁、デジタル庁などカタカナを使った今風の省庁も増えた。
そして今年新しく「こども家庭庁」が発足したのだ。
今回はこども家庭庁の役割と発足背景などを確認してみよう。
こども家庭庁とは何をするところなのか?
こども家庭庁は、その名前の通りこどもや家庭に関する政策を統括するための機関です。
この機関の役割は、こどもの福祉や保護、教育、家庭環境の向上など、こどもや家庭に関する様々な課題に取り組むことです。
こどもや家庭に関する政策は、元々厚生労働省や文部科学省などの複数の省庁が担当していますが、
それぞれの省庁間での連携や情報共有が不十分であるという課題でありました。
こども家庭庁の設立により、こども、家庭に関する問題をまとめて対応することができるようになったのです。
目的と背景
発足の目的はこどもの貧困対策や虐待防止、学校教育の充実などの対策のためと言われています。
これら問題に向き合い、こどもたちの健やかな成長を支援し、子育て環境の充実を図ることです。
また発足の背景には様々な問題が原因でした。
少子化
日本は数十年単位で少子高齢化が進んでいます。
そのため、国の存続には若い世代の増加、成長が不可欠です。
特に少子化により例えば、子育てを相談できる人が周りにいないなど、頼れない状況が生まれてしまいます。
児童虐待、いじめ
児童虐待、いじめは子供の成長、生死に大きく関わる問題です。
特にコロナによる生活変化により、子供、親の負担大きく、家庭内暴力、いじめが増加してしまいました。
不景気などによる貧困と経済的圧迫
日本は数年間不景気であるとされています。
不景気は誰にとっても辛いものですが、特に子育て世代には死活問題です。
子供にちゃんとした食べ物を食べさせられなくなったり、就学が制限される。
またそもそも負担が大きいため子供を持てないなどが起きてしまいます。
これら問題は国全体の問題でもあるため子ども家庭庁の役割がいかに大きなものかが分かります。
子ども家庭庁は具体的どのようなことをしている?
さて今年度発足ため、活動期間はまだ短いですがこども家庭庁はさまざまな政策を打ち出しています。
母子保健、不妊治療の相談支援
こどもが健やかに育つ社会の実現を目指し、妊産婦健診や乳幼児健診、産後ケア事業などを通じたサポートの推進をする。
また、性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、不妊症・不育症への相談支援を推進します。
など子供を作りやすい環境に取り組んでいる。
Jリーグと協力したイベント
こどもの健やかな成長を促進するために、Jリーグを応援サポーターとして様々なイベントを企画した。
イベントの中には試合に招待したり、選手と触れ合えるようなものもあり、今後その活動は活発になっていくだろう。
しかし、批判的な声もあがる
将来的には子供の支援は国を支えるうえではとても大事なことだかが、
こども家庭庁の活動は果たして効果的なのかという疑問もかなり挙がっている。
予算5兆円?
さて、こども家庭庁を数値的に見てみよう。
2023年4月発足したこども家庭庁。
発足時の職員は350人であり本年度当初予算は4兆8104億円となっている。
ちなみに2021年に発足したデジタル庁の予算は約5000億円となっており、こども家庭庁の予算の異常な額が伺える。
もちろん、こども、家庭の支援は急務であり、今後取り組むうえでは最終的にそのくらいの予算はかけるべきかもしれない。
しかし、年間予算で約5兆円を投じて行ったのがさっきのようなことだけっというのは今後が少し不安になっていく、、、
5兆円を直接若者にばら撒いた方が解決しそう
さて今年新しく発足したこども家庭庁について見てきた。
少子高齢化、不景気など未だ暗い課題を抱えている日本において
子育ての充実化は急務であり、国の存続に関わることだろう。
しかし、発足したこども家庭庁の活動はまだまだ国民に理解される、支持されるものとは言えない。
長い目で政策を頑張ってほしくもあるが、
数十年前から少子化問題はあったのに今になってやっと発足したこども家庭庁に残された時間は少ないのかもしれない。
このページを最後まで読んでくださってありがとうございます。
よろしければ、他にも色々と考察しているので読んでみてください。
また、私のLINEアカウントでは、本当に安心して行える資産運用の方法をお伝えしています。
ご興味ありましたら、ぜひ友だち登録をしてご連絡ください。
きっとあなたの為になると思います。