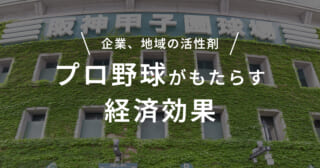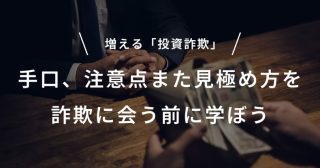2014年7月に政府は臨時閣議で、集団的自衛権を使えるようにするため、憲法解釈の変更を決定した。
良くニュースでは集団的自衛件と呼ばれているがそもそもこれは一体何なのだろう、、、
今回はそんな疑問にお答えできる記事となっておりますので是非、閲覧をお願い致します。
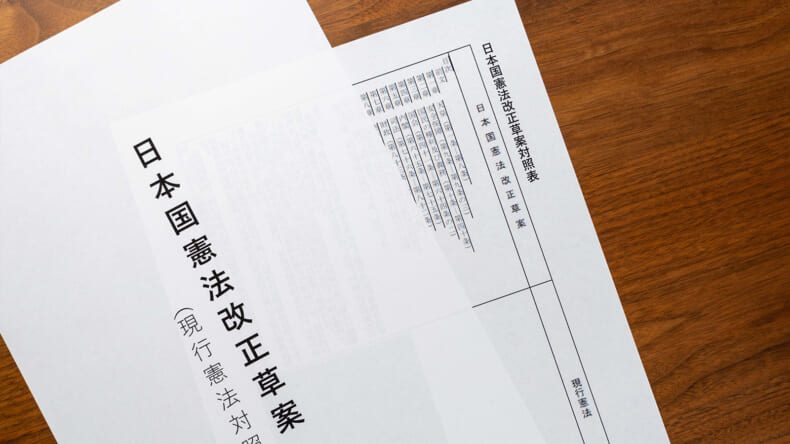
集団的自衛権とは
集団的自衛権とは、その成り立ち
集団的自衛権とは、自国以外で密接な関係にある別の国などが攻撃を受けた際に防衛という名目で自国軍が他国に援助し武力行動を行うという国際法上の国の権利である。
成り立ちとしては冷戦時代にさかのぼる。
1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された国家の権利であり、当時の世界が二極化し、隣国同士でも守りあわないといけない時代は背景が見えてくる。
日本国おける集団的自衛権
さてそんな集団的自衛権だが、わが日本国も1951年に連合国との間にサンフランシスコ講和条約が締結された際に、同様にその権利が認められた。
強い外国諸国との繋がり,国の成長のためにも足並みを揃えることは大事であったが日本においては一つの問題が発生した。
憲法9条との矛盾
憲法9条
第二次世界大戦終戦後、日本国はこのような戦争の災禍を作らないためにも憲法に平和への決意を示した。それが憲法9条である。
憲法9条は自国での防衛をする上での必要最低限の武力以外の放棄、戦争行動の放棄など、戦争という行為に対する一切の否定が込められた内容となっている。
この憲法は作られてから現在に至るまで変わることなく、日本という国が平和の象徴という根幹を成しているもの捉えられるだろう。
集団的自衛権との関係
自国を守るための自衛権、武力のみを持つ日本国だが、ここで一つの問題が発生する。
それは集団的自衛権とのぶつかりだ。
集団的自衛権は隣国など自国以外を守るために自国の武力を持って防衛活動をする権利であるが、果たしてこれは自国を守るだけを誓った憲法9条としてはどのように捉えるべきなのだろう。
また、最終的に武力を他国に送らなくても政治的判断が鈍る要因ともなりかねないため、解釈の曖昧はかなり問題となる。
実施された解釈変更
2014年まで日本国は憲法9条に抵触するという理由で集団的自衛権は認められませんでした。
しかし安倍内閣により、日本は他国が攻撃を受けた場合に、その他国を守るために武力行使を行うことができるようになりました。
この解釈変更は、日本の安全保障政策の転換を意味しており、日本がより積極的に国際社会での貢献を果たすことを目指しています。
特に大きくなく中国をはじめとした大陸諸国の圧力のためにも。アメリカとの連携が急務と考えられ、このようなことになったのではないだろうか。
しかし、集団的自衛権の解釈変更には否定的な意見も多く、その原因の一つはやはり憲法9条に関連するものである。
隣国の自衛の支援とはいえ、突き詰めれば戦争行為ではないか、他国戦争に巻き込まれてしまうリスクなど平和の国としての日本を揺るがすものではないかと、今日でも議論は絶えません。
まとめ
集団的自衛権の解釈変更は、日本の安全保障政策に関する重要な転換点でした。
背景としては、日本が国際社会でより積極的な役割を果たす必要性や、中国や北朝鮮などの脅威への対応が挙げられます。
この変更により、日本は他国の攻撃に対して自衛の範囲を超えた防衛行動を取ることが可能となりました。
これにより日本の安全保障政策の柔軟性が向上し、日米同盟の強化や国際協力の促進がされることでしょう。
このページを最後まで読んでくださってありがとうございます。
よろしければ、他にも色々と考察しているので読んでみてください。
また、私のLINEアカウントでは、本当に安心して行える資産運用の方法をお伝えしています。
ご興味ありましたら、ぜひ友だち登録をしてご連絡ください。
きっとあなたの為になると思います。